――今回、大西麻貴さんがゲスト審査員として参加されます。大西さんの作品の印象を教えてください。
大西さんのプランで最も印象に残っているのは「SDレビュー2007」の展示会場で拝見した「千ヶ滝の別荘」の模型です。大西さんが百田有希さんと共同設計されたもので、会場の中で独特の存在感を放っていました。森の中でふと出会ってしまった山の主のような存在は、人だけでなく、周辺の生き物たちも安心して集まってきそうで。とんがり屋根だけが浮いたような建築は、都心にあったら奇抜ですが、森にあると擬態して消えてしまう。自然に近い状態を建築で探られているのかなと面白く感じました。

――初めて建築家である大西さんがゲスト審査員に加わってくださいますが、期待することはなんでしょうか。
以前、対談をした際、「ある」と「いる」についてお話しされていました。「いる」ような建築を実現できるのは、野生的感性を大切にされているからではないかと想像します。触覚的、身体的なことから建築を捉えているからこそ、生物的な何かが宿るのでしょうね。元々の固定概念を揺さぶってくる大西さんの思考が審査で覗けることが楽しみです。
――第18回は「つながるしるし」というテーマですが、どのような印象を受けましたか。

見えていない、または見てないだけで、意識してみるとあらゆるところにつながりはありますよね。たくさん探せてしまうからこそ、その中ではっとするつながりを手繰りよせることは、案外難しいかもと感じています。
――「つながる」というキーワードから想起することはなんですか。
昆虫の研究者と仕事をしたとき、「虫を探すには、虫を見つけようとするのではなく、その虫が食べる植物を探すと見つかる」と教えてもらいました。なるほど!と。実際にオトシブミを探すために先ずは居そうな木を見つけてからその葉っぱに目を向けると、確かにその昆虫を発見できました。米粒大の昆虫を大きな森で探すのは困難ですが、まあまあの大きさの木なら探すことはできる。終点に直行しようとするのではなく、中間ポイントに先ずは向かう。つながり方の面白さを実感した思い出です。
――しるしに関係なく、つながると面白そうだと感じるものはなんですか。
最近、ここ5年間の自分の研究室の主な出来事を一枚の紙にみっちりと描きました。当然と言えば当然ですが、何の脈略もなく生まれてくる仕事は一つも無く、関わりの連続で形成されていました。私が描いたものは「つながりの図譜」であると理解しました。それは、一直線のしりとりみたいなつながりではなく、網を立体的に張り巡らせたようなつながりです。いつか自分では想像もつかないような仕事に網目の先でつながっていたら嬉しいですね。
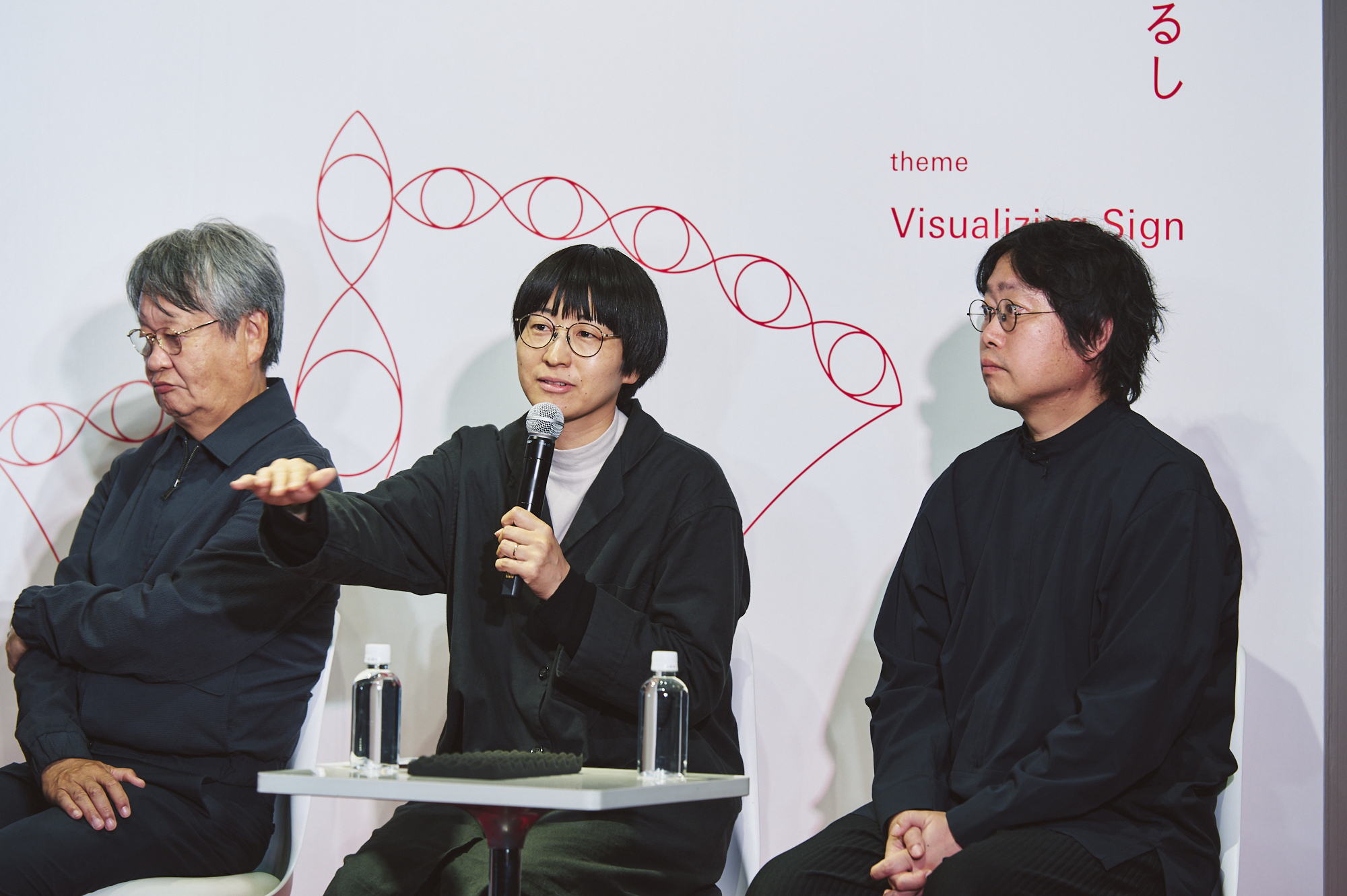
――もし最近、しるしについて新たに気づいたこと、考えたことなどがあれば教えて下さい。
私のつくったものに「動画に落書き」という作品があります。鳥をスマホでムービー撮影し、その動画上にアーチや扉や壁などのパーツを描く、極めてゆるいあそびです。そのパーツは、言い換えれば「認識を変換するしるし」です。しるしの有無によって、同じ動画が全く別の物語に見えてくる不思議。最近は、鳥を見つけると実際に描かずとも頭の中にアーチの図像が浮かぶようになりました。これもまた頭の中に刷り込まれた一種の「しるし」と言えるかもしれません。
取材・文:角尾舞