――大西麻貴さんについて、ご自身や彼女の作品の印象を教えていただいてもよろしいでしょうか。
大西さんは、インクルーシブな感覚のある建築を作られている方だと思います。世代的には「私たち」を主語に据えている感じがしますよね。これまでの建築家はものすごく「私」が主語だったと思うんです。「私」はこういう考え方で、「私」はこういう建築を作る、というような非常に際立った「私性」の強さを持っていた。しかし主語を「私たち」にしていかないと、いろいろなものが包含できないし、社会全体の問題も解決できない。今直面しているのは「私の問題」ではなくて「私たちの問題」ですよね。海洋汚染も戦争も、社会全体の思想を「We」という主語に変えていかないと難しい。若い世代はこの辺りが敏感で、主語を私たちに変えていっている。そんな世代を代表する建築家の肌触りを感じます。
――今回、初めて建築家の方に審査員に加わっていただきますが、期待される変化はありますか。
いわゆるデザイナーばかりが集まって審査するよりも、領域的に広く捉えた方がいい気がしますよね。特に「つながる」というテーマだと、いわゆる文房具とかプロダクトデザインとか、そういう枠を超えていくと思うのです。枠組みもだんだん緩やかになってきているので、いろいろな方が参入してくるのはいいなと思います。判断の範囲が広がるし、柔らかくなるんじゃないかな。

――「つながるしるし」というテーマについて感じることはありますか?
「私たち」の時代といいながら、現代はこれ以上ないくらい分断されていますよね。個人を意味する「indivisual(インディヴィジュアル)」の語源は「これ以上分割できない」ということですが、まさにそういう時代です。
今の日本は、単身世帯が圧倒的に多いんですよ。若者も含めて、一人暮らしが最も多い。コミュニティもなくなって、住まい方もインディビジュアルになってしまったところから、どうやって新しいつながりを作るかが、新しい社会の仕組みとして必要になってきているのです。
つながるとは、ただジョイントすることではなくて、いろいろなところに関係の触手を伸ばしていくということ。ある意味で、時代的には非常に重要な言葉かもしれません。
――今回のポスターなどのビジュアルに関してコンセプトはありますか。
ビジュアルについて聞かれるといつも困るんですが、ポスターでの募集は、あまり大声で叫びたくないんです。「やりますぞ!ドカーン!」ではなく「やるよ」って、ちょっと小声でささやくくらいの方が、毛細血管までメッセージが届く気がして。
また、決めつけないことも大事だと思っています。「つながる記号」みたいなイメージを作ってしまうと、発想をある方向に強烈にディレクションしてしまう感じがするので、「これはなにかしら」と思うような小さな謎がありつつ、そのなかにつながる印象もあるかな、くらいのグラフィックですかね。

――どんな「つながるしるし」を期待しますか?
現代は本当にレスポンスが早いから、超スローなつながり、みたいなのが面白いと思うんですよ。SNSもそうだし、たとえば博多のおばあちゃんと連絡したいときも、電話で「おばあちゃん元気?」って話すのが一番早い。
でも本当は押しつけがましくなく、何かそこにつながりが発生する、みたいなのが面白いと思うんですよね。毎晩電話するような窮屈さではなくてね。僕も田舎の母親のことは気になるけれど、頻繁に電話するのは照れくさいんです。いろいろとしつこくは聞きたくない。でもどこかでじんわりケアしている感じは持っていたい。その方法はなんでしょうかね。つながるというのは、ものすごくおおらかなことなのかな、と僕は思うんです。そういうスローな視点を見てみたいなとは思います。
それから、学生と一緒に宇宙葬について考えたことがあります。お骨を小さなかけらにして、コンパクトなカプセルに入れて、ロケットで打ち上げて地球外の軌道に向けて放出するという、一連のシステムやデザインです。僕が死んだ後に「原さんは今、宇宙で飛んでるんだ」と誰かが思ってくれることは、一つの祈りにつながる気もしませんか?
――亡くなった方とのつながり方の提案も、面白いですね。
お墓もそうですが、人と人のつながり方に関しては、恋愛や夫婦というかたちだけでなくもっと違う関係性も考えられますよね。たとえば、3年間の激しい恋よりも、30年間、毎月1回手紙をもらう関係の方が、きっと人生で重くなります。親からもらった手紙は捨てられないけれど、メールは多分消えます。肉筆の手紙に勝てるような「つながるしるし」はなかなかないかもしれない。
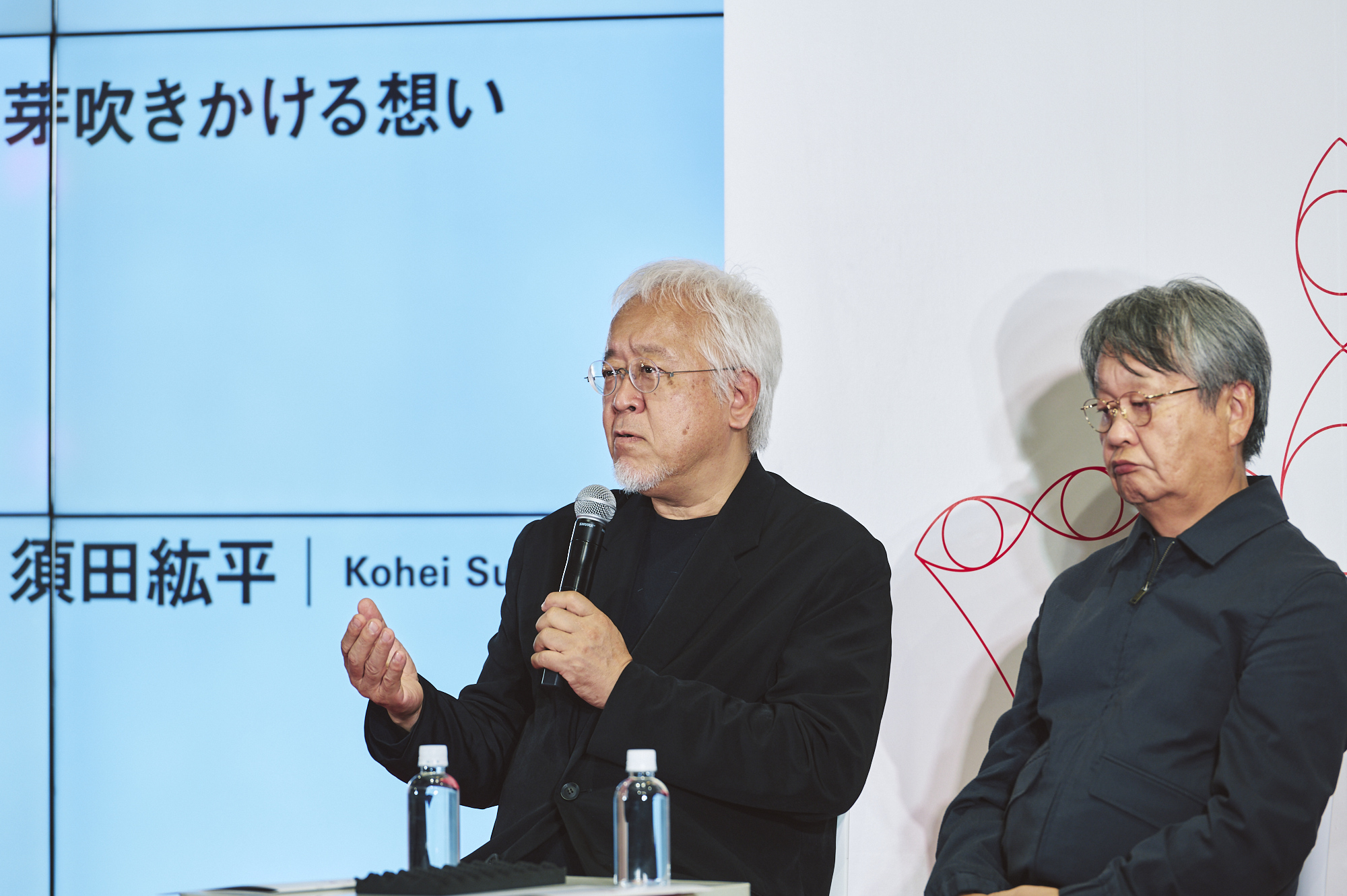
――最近、他に気になる「しるし」はありますか?
石に十文字で紐を結んで、ぽつっと置いておく「留め石」ってありますよね。なかなか日本的なしるしだなと思っています。石が置いてあるだけで、本来の意味がわからなくても、その先には入れませんよね。何かデリカシーを喚起され、入るとなにか良くないことが起こるのではないかと想起させる。千利休くらいの時代にできたと言われていますが、不思議なものが日本文化の中にはあるなと感じています。「ここに入っちゃいけない」というしるしだとは明言されてはいない。でも置かれていると、入れない。バチがあたりそうな、怖さを伴ったしるしです。そういうものが暗黙に機能している社会というのは面白いですね。
取材・文:角尾舞