2025年10月10日、第18回SNDCの表彰式が開催された。今回はこの表彰式の後半で行われた、中村勇吾氏、原 研哉氏、三澤 遥氏、大西麻貴氏、そして舟橋正剛氏の審査員5名によるクロストークをレポートをする。なお深澤直人氏は当日不在のため、ビデオメッセージというかたちで受賞者にエールを送った。モデレーターは、第18回SNDCのコピーライティング・インタビュー記事等を担当している、デザインライターの角尾 舞が担当した。

―― 受賞された皆さま、あらためておめでとうございます。今年は1,681人という過去最多の応募数でした。それでは早速ですが、特別審査員の舟橋社長より順番に、今回のコンペ全体の印象についてお伺いできますか。
舟橋 これまで18回開催して、これだけグランプリを決めるのに激論を交わしたのはおそらく初めてではないでしょうか。それだけ良い作品が多く、「つながる」という視点に対してすごく深い考察をされていました。僕自身は、少しずつコンペをハンコから離したい、とコメントでも何度も出していますが、ハンコというジャンルの中でもびっくりするような作品が非常に多く、大変楽しく審査をさせていただきました。ありがとうございました。
中村 すごく楽しい審査でした。今年は特に、真剣に遊んでいる作品が多くて。タモリの名言で「真剣にやれよ!仕事じゃねぇんだぞ!」ってありますが、そういう感じですね。今日の表彰式でも分かりましたが、仕事の外で新しいトライアルをしようという、真剣に遊ぶ精神がありました。とてもいい会だったと思います。おめでとうございます。

原 最終審査会の後半はほぼディスカッションで、どの作品をグランプリにすべきか、どういう考え方でそれを推すのか、という審査員同士の視点の競い合いになります。SNDCは特にそうで、応募した方々の熱意と、審査員のデザインに対する考え方や、その時々の思いが一緒になって、賞が決まっていく。だから「どれに賞を与えるか」というところに、このコンペの面白さがあると思っています。 その意味で、ごく身近なものからデザインの鮮度みたいなものを取り出すことが役割だと思っています。そういう現場は、本当に楽しいですよね。今年も充実した審査ができました。11名の受賞者の皆さま、本当におめでとうございます。
三澤 皆さん、おめでとうございます。私も今年は高揚感があって、ワクワクした気持ちが残り続けた審査会でした。ぜひ皆さんに全部見てほしいぐらい、白熱した議論がありました。すごく面白くて。私が話したことに対して深澤さんが「分からない」っておっしゃったり、皆さんの作品を通して今の時代が見えたり、ものの価値って今どこにあるんだろうと考えさせられたり、そういうことに触れられる機会でした。ありがとうございました。
―― ありがとうございます。今年ゲスト審査員として初めてご参加いただいた大西さん、いかがでしたでしょうか。
大西 皆さん、おめでとうございます。私は普段は建築の設計をしているので、プロダクトの審査をするのは初めてに近い経験だったのですが、「つながる」というテーマで、こんなに多様な回答が出ることに驚きながら、とても楽しく審査をいたしました。 すごくダイレクトに身体に訴えかけて、思わず使いたくなってしまう感覚だったり、ものとしての佇まい自体が非常に美しいものだったり。「つながる」というテーマに対してどのような回答をするのか、その意味を考えたときにすごく納得させられたり、深いなと思わされたり。そうした視点が重なり合いながらグランプリが決まっていく審査の過程が、非常に楽しかったです。

―― 本日ご出席が叶わなかった深澤直人さんより、ビデオメッセージが届いてますので、ここでご紹介いたします。今回の総評と、それぞれの作品についてコメントをいただいております。
深澤 今年の「つながるしるし」は難しいテーマでしたが、素晴らしい人々の参加によって、 とても面白いものがたくさん出てきました。応募作品の成長に驚いて、感動しています。おめでとうございます。 グランプリの 「ライン印」は、見たときに本当に驚きました。 3センチくらいの線を印として使うものですが、ものとしては非常に単純です。でもその使い方の広がりが、拝見したときに自分の中で猛烈に広がりました。予測して使うのではなくて、使うにつれて、こういう使い方もあったのかと、創造性、可能性が広がることにすごく驚きました。線というものには力があります。たとえば、文字の上に引くときと、文字の下に引くときでは意味が変わります。一つは間違いとして消すという意味で、もう一つはハイライトとして強調することですよね。これは大発明で、大きな気づきを与えてくれるものです。素晴らしいアイデアだと思います。 深澤賞は「Pum!」という、もちもちした触感の印です。過去に自分が与えた賞を考えると、ほとんどがものと使う人の関係性を中心に考えがちでした。この作品は感触があまりに優しく気持ちよくて、赤ちゃんの頬を触るように指で押すイメージが強かった。「可愛いね」って推すような仕草、インタラクションを感じて良かったです。これまでのシヤチハタの印とは全く違う次元の、新しいインターフェースです。この接触感をよく作ったなあと。芯があるけどちょっと柔らかい、その素材の研究もなさったと聞きました。 おめでとうございます。

―― では続いて、各受賞作品についての講評です。グランプリ の「ライン印」について、舟橋社長よりコメントいただけますか。
舟橋 表彰式で作者の方もおっしゃってましたが、本当にシンプルな作品なので、僕は最初は「これ売れるかな……」って実は思っちゃったんですね。でもそのあと審査員の先生たちの大議論が始まって、この一本の線のスタンパーの使い方、つながり方とデザインに対する深さを思い知らされ、反省しました。本当に、いかようにでも使えますね。紙が減っていく時代に、使い方をいろいろと提案できるものが「つながるしるし」というテーマに対してのグランプリとして選ばれるのは、非常に意義深いと思っています。

―― 続いて審査会場でおそらく一番試し押しされていた、三澤さんよりコメントいただけますか?
三澤 一本の線がすごく脳みそを刺激してくることに、実際に触れたときに分かりました。佇まいがすごく絶妙で、もうちょっと短かかったり、細すぎたり太すぎたりしても「ライン」って呼べないかもしれない。絶妙な一単位を、一つのプロダクトにしている気がしました。永遠に遊べるくらい人を触発してくるものだなと思い、すごく推しました。
―― 大西さんはいかがでしたか?
大西 何かをつなぐことを考えるとき、A地点とB地点を線でつなぐ、というのが一番ダイレクトな答えだと思いますが、一本の線を複数つなげることができるハンコというのは、テーマに対して非常にダイレクトな答えだな、というのを審査中に徐々に理解できました。実際に押してみると、絶対に二つ目三つ目を押したくなってしまうのが魅力でした。
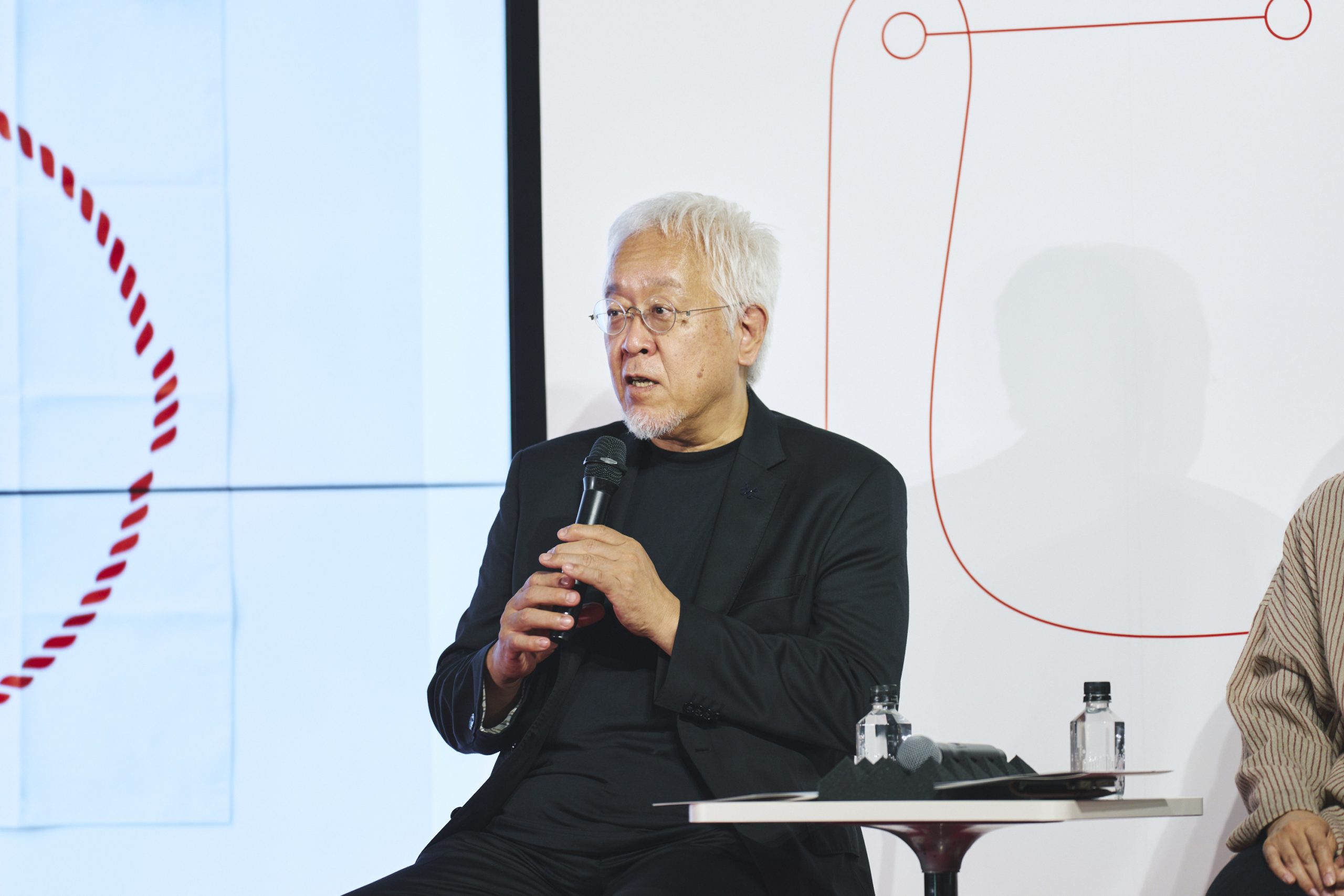
―― 準グランプリの作品についての講評をお願いします。「hitohira」について原さんよりコメントいただいてもよろしいでしょうか?
原 準グランプリの2点とグランプリは本当に競ったんですよね。コンペ自体が少しずつハンコから離れようという意図がありますが、「hitohira」はハンコなのにハンコから離れています。透明アクリルの中に漢字が一画ずつバラバラになって散っていますが、その風情がとてもきれいで、置いてある印象がハンコのイメージを根底からくつ返してしまう美しさがありました。 上から見ると、ちゃんと名前が見えるんですね。僕はこういうハンコがあったらほしいと、本当に思いました。これは、製品としての完成度。グランプリの作品は哲学ですね。哲学に賞を出すか、製品に賞を出すかみたいなところに、審査員に責任がありました。根源性に軍配は上がりましたが、私は「hitohira」という作品、とても素晴らしいと思っています。
―― ありがとうございます。三澤さんも非常に高く講評されていましたね。
三澤 一次審査の書類で拝見したときから美しいと思っていましたが、実際に会場で出合ったとき、すごい精度と完成度で、どうやって作ったんだろうと思いました。しかもただ文字が散らばっているだけじゃなくて、上から順に画数になっている。書く文字がハンコのかたちで押せる、という時間軸が凝縮されたプロダクトの表現は、とても惹かれるものがありました。
―― 続きまして、もう一つのグランプリ作品「どすこい!シート」」、こちらは非常に高く評価された中村さんにお伺いしたいと思います。
中村 第一印象で「グランプリだな」って思いました。第一に、ドンとスタンプを押すその発想がすごく明快で、何かの行為を促すサインを「地面に押す」みたいな。こういうレジャーシートにアイコンを乗せて、いろんなところにモバイルに展開できる商品性も高い。もちろん相撲の土俵を描くのも面白いですが、たとえば「中村」って書いて、花火の場所取りなんかに使えたり。そういう地面にドンっと刻印するみたいな発想の強さ、インパクトを瞬間的に感じました。三澤さんに「相撲しませんか」って言って断られるなど、僕のプレゼン力不足で惜しくも準グランプリですが、おめでとうございます。

―― 大西さんは、いかがでしたか。
大西 中村さんの一言で急浮上してきた作品で、それまで魅力にしっかり気がつけていなかったのですが、「つながるしるし」を空間化したような作品だと思いました。普段、建築の仕事をしていて空間にまつわる仕事をしているのに気づいてなかったって思わされて、一本とられたなと。なんだかナスカの地上絵みたいに、大地に印を刻みつけることを誰でもできるプロダクトで、非常に魅力的だと思いました。
―― ありがとうございます。それでは、各審査員賞に移りたいと思います。舟橋社長の特別審査員賞「YA.JIRUSHI→」からお願いします。
舟橋 シヤチハタはしるしの付加価値を高め、広げていくことを非常に大切にして事業展開していますが、まさにそれを体現したようなご提案です。矢印の短い付箋をテープで一つずつ貼っていくものですが、矢印によって次の作業につなげるという今回のテーマにも寄り添っていますし、ありそうでなかった。過去の商品の応用でも製品化できそうですし、飛びつきました。
―― 中村賞の「気配灯」についてお願いします。
中村 モニターとカメラが内蔵したものが、それぞれ離れたところでつながっている、という作品です。映像が動いて、気配だけを感じる。スクリーンがあって、カメラがあって、それを離れたところでつなげよう、というアイデアはメディアデザインの世界で結構あるし、遠隔地からペットやおじいちゃんおばあちゃんをリモートで様子見ようというプロダクトも結構ある。さらにいえばコンペだと「気配のコミュニケーション」みたいなアイデアも割とあるんですが、この作品は、めちゃくちゃちょうどいい。みんなが漠然と思っていた、ちょうどいい組み合わせだな、と思いました。否定的なわけじゃなくて、今、みんなが求めて考えていることを一番ちょうどいい形で具現化するのはすごい能力だと思うので、そこを高く評価しました。あと、デモがすごく良かったです。ちゃんとミニチュアのカメラがついてて、裏にarduinoみたいなのが入っている。それを見てなんか、最近のデモはやっぱりレベルが高いなと、その心意気も僕は印象に残りました。

―― 続いて原賞の「苗字カルタ」についてお願いします。
原 なんて読むか覚えられないくらい、難しい読み方の名前がありますよね。そういうものをよく見つけたなということと、それを印章のような方法で表現しているところが興味深いです。裏側がつやつやした黒になっていて、ハンコの背とフェイスが一枚の紙のなかで共存しているところも捉え方として非常に面白いと思ったんです。カルタとしてはもちろん、神経衰弱のような遊び方もできるかもしれません。学生とゼミ旅行に行って、本気でやると盛り上がるかも、と思いました。とても僕が気に入った作品です。
―― 続きまして、三澤賞の「ハンコドリ」についてお伺いできますか。
三澤 自分も鳥を飼っているので、鳥の角度というか佇まいというか、「インコの角度」に惹かれました。造形は全く鳥じゃないのですが「鳥がいる」って思ったんです。鳥っていろんなところに飛んでとまります。壁面や天井にもとまってしまうような存在感が、引き出しから出すハンコとは違う意味を持っていると思いました。なんとなくですが、洗練された家よりも、ものが大好きで、溢れかえっているような、いろんなものに囲まれている人の家に相性が良いイメージが沸きました。名前で呼びたくなるような、愛着が現れていて、とても好きです。
―― 最後に、大西賞の「笛印鑑」についてコメントいただけますか。
大西 「つながる」というテーマを考えて、音にして誰かにメッセージを発する、というアイデアがまず良いなと思いました。私自身、震災復興の仕事に関わることが多く、防災においてホイッスルってすごく有効だと聞きました。ただ私も持っているのですが、なかなか毎日持ち歩かなくて、家に忘れちゃいます。でも大事なハンコと一緒になっていれば、日常的に持ち歩くべきものになるので、非常にいいアイデアだなと思いました。

―― ありがとうございます。今回、今までで一番応募者の平均年齢が若かったり、受賞者の方に女性が非常に増えたりして、そこには時代性みたいなものもあるかなと思うのですが、そのあたりの感触について、原さんにお話伺ってもよいでしょうか?
原 やっぱり徐々に、ハンコから離れてきていますよね。これまである意味ではオーセンティックな感覚だったのが、今年の受賞者なんかを見ていると、ハンコからの離れ方がすごく小気味よいですよね。また僕は美術大学で教鞭を執っていますが、8割ぐらいの学生が女性ですから、当然かなと。むしろまだ男性が多いんじゃないか、と思うぐらいにこれからのクリエイティブは女性が担っていく局面が増えてくると思いますよ。
―― 大西さんに伺いたいのですが、建築のコンペとプロダクトのコンペで見えてくるものや、違いはありましたか?
大西 建築のコンペは会場に実物がないので、こういうものになるんじゃないか、って想像で補って審査します。しかし、プロダクトの審査はモックアップがあって、紙面で見ていたものが「もの」になったとき、こんなに身体に対する訴え掛けがあるんだということを感じられたのがすごく面白かったです。
―― 中村さんと三澤さんのお二人が、モックアップの完成度についてコメントされていました。それについて、お二人から伺えますか?
中村 クオリティが上がって嬉しいな、ということですが、3Dプリンタをはじめ、いろいろなツールが出てきているので、それに伴ってプロトタイプのレベルも上がっています。プロトタイプよりも実動デモみたいなものに、これからどんどん近づくと思います。

三澤 逆に、一次審査ですごくいいなと思って実物を見るのを楽しみに会場に来たら「あれ?」みたいなのもありましたね。若い方がたくさん応募されたからだと思いますが、アイデアはすごくキラキラしているけれど、ものの力がまだ追いついていない。完成度の低さがノイズになってしまうと、どうしても純粋にものに集中できない。でも受賞された作品はどれもしっかりと作られていて、たぶん皆さんたくさんプロセスがあって、何度も試作してやっと出したような精度の高さを感じて、プロの仕事が混ざっているなと審査を通して感じました。
―― 原さんはSNDCの第一回から審査員をして頂いていますが、そこから休止期をはさんで、すでに26年経っています。変化の面白みはございますか?
原 どこがどう違うのかは分かりませんが、ものに対する思考の精度や密度、モックアップの加工においても、自分の頭のなかにある形状の「素晴らしさ」を外に出す技術が上がってますよね。受賞作品の変化は世の中や社会の人々の考え方の違いみたいなものが現れてきている感じがあるので、一回歴史を辿ってみると、すごく面白いと思います。来年も楽しみです。

―― 最後に舟橋社長より、来年に対しての意気込みをお願いします。
舟橋 今回の受賞作品も、一つでも多く商品化できるように頑張っていきたいと思いますが、19回もできれば、「しるし」にこだわっていきたいですね。先ほど審査員の皆さんがおっしゃったように、ここ2、3年はレベルが非常に高くなっていると感じます。僕はハンコから離れたいって言いましたけど、意外に受賞作の多くはハンコです。でも原さんがおっしゃったように、確かに、ハンコではあるけどハンコからの離れ方が気持ちいいと思っています。ぜひ来年も期待しています。本日は、ありがとうございました。
―― 審査員の皆さま、どうもありがとうございました。
構成:角尾舞 撮影:井手勇貴